はじめに
和食を作るときに「調味料を入れる順番は大事」と聞いたことがある人は多いはず。
昔から
「さしすせそ(砂糖・塩・酢・しょうゆ・味噌)」
という覚え方もありますが、実際になぜこの順番が大事なのか?なぜ入れ方で味が変わるのか?
ここでは料理人としての経験と調理科学の観点から、調味料の順番をわかりやすく解説します。
コツ1:砂糖は最初に入れる
砂糖は分子が大きく、後から入れても素材に浸透しにくい調味料です。
だからこそ 一番最初に入れて素材に甘みを含ませる のが鉄則。
焼き鳥屋のタレ作りでも、必ず最初に砂糖を煮溶かしてベースを作っていました。後から足しても味が浮いてしまい、全体のまとまりがなくなるんです。
コツ2:みりん・酒で風味とコクを出す
砂糖の次に入れるのが、みりんや酒。
みりんは糖分とアルコールを含んでいて、照りやコクを出す役割があります。酒は臭み消しや旨味の抽出に効果的。
この2つを早めに加えることで、素材に風味が染み込み、味わいがまろやかになります。
焼き鳥のタレや煮物も「砂糖+酒+みりん」でベースを整えてから、しょうゆで締めるのが基本でした。
コツ3:しょうゆは最後に入れる
しょうゆは香りが命。煮込みすぎると風味が飛んでしまいます。
だから 仕上げに近い段階で加える のが正解。
たとえば肉じゃが。最初にしょうゆを入れて煮込むと、香りは飛び、味も角が立ちやすい。でも最後に入れると、香りも味も生きて、深みが出ます。
コツ4:「さしすせそ」の本当の意味
「さ=砂糖」「し=塩」「す=酢」「せ=しょうゆ」「そ=味噌」
これはただの語呂合わせではなく、浸透しやすさと風味の特性に基づいた順番です。
- 浸透に時間がかかる砂糖は最初
- 素材にしっかり入りやすい塩はその次
- 酸味の酢は加熱で飛びやすいので後半
- 香りを残したいしょうゆ・味噌は最後
この法則を理解していると、和食だけでなく洋食・中華にも応用できます。
実践例:肉じゃがの場合
- 鍋に砂糖を入れて肉を炒める
- 酒・みりんを加えて風味をプラス
- しょうゆを回しかけ、仕上げに風味を残す
この流れで作ると、素材に甘みがしっかり入って、しょうゆの香りも生きた仕上がりになります。
まとめ
調味料の順番を意識するだけで、いつもの料理が格段に美味しくなります。
- 砂糖は最初に:浸透に時間がかかる
- みりん・酒は中盤に:風味と旨味をプラス
- しょうゆは最後に:香りを残すため
「さしすせそ」は単なる語呂合わせではなく、理にかなった調理科学。今日から意識して使ってみてください。
※レシピ考えるときは、
Kindle Unlimitedで料理本を流し見してネタ拾いしてます。
小説のサービスって思われがちだけど、意外とレシピ本も多いです。(僕は小説も読むので一石二鳥)
30日間の無料体験・お得なキャンペーンあり

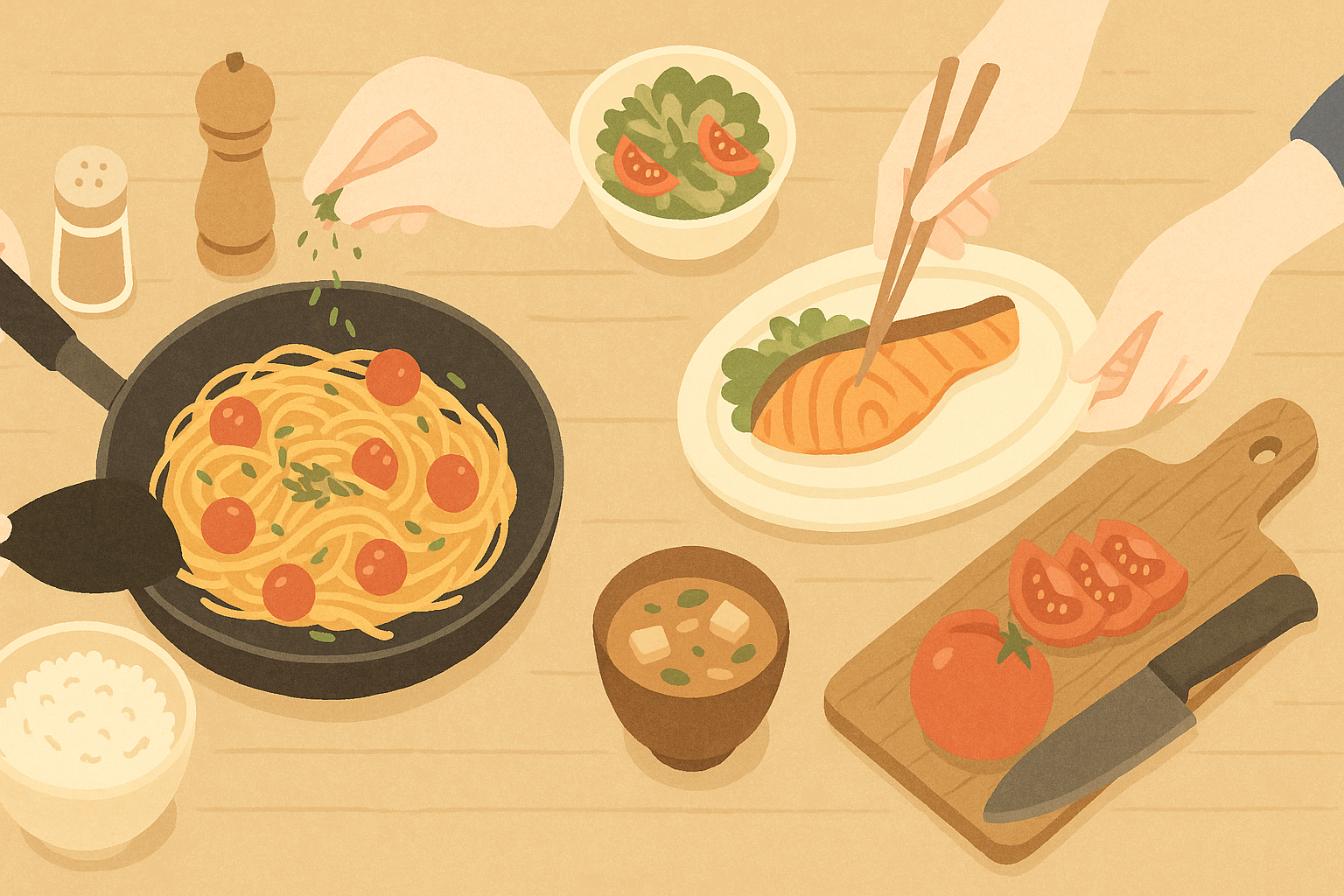


コメント